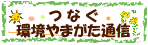2018年05月28日
水活~飛島クリーンアップ作戦に参加
【環境科学研究センター】
こんにちは。2回目投稿の T です。またまた、海のお話です。
今年で18回を数える飛島クリーンアップ作戦(5月26日(土))に、今年もボランティアとして参加しました。(トータル10回目?)
酒田海洋センター前で、参加受付、開会セレモニーの後、定期船「とびしま」に乗船。
1時間15分で、飛島に到着。

船を下りたら、荒崎海岸に移動します。

海岸に着いたら、さっそくゴミ拾い開始。
発泡スチロールやロープ、ペットボトルなどプラスチック類の漂着が多いようです。

拾ったゴミは袋に入れ、仮集積所へ集めます。

荒崎海岸は車が入れないので、バケツリレーで、仮集積所から島の中央部へゴミ袋を運びます。

一連の作業の後、昼食、自由時間を過ごし、閉会セレモニー。

再び定期船「とびしま」に乗り、飛島を後にします。
ウミネコが見送ってくれました。

船から見た鳥海山です。

この日の参加者は230名、集めたごみは約2.2トン(主催者発表)とのことです。
天気は快晴でしたが、あまり暑くもなく、さわやかな汗をかきながら飛島をきれいにしたという達成感が得られた1日でした。
来年、是非みなさんも参加してみませんか。 T
こんにちは。2回目投稿の T です。またまた、海のお話です。
今年で18回を数える飛島クリーンアップ作戦(5月26日(土))に、今年もボランティアとして参加しました。(トータル10回目?)
酒田海洋センター前で、参加受付、開会セレモニーの後、定期船「とびしま」に乗船。
1時間15分で、飛島に到着。

船を下りたら、荒崎海岸に移動します。

海岸に着いたら、さっそくゴミ拾い開始。
発泡スチロールやロープ、ペットボトルなどプラスチック類の漂着が多いようです。

拾ったゴミは袋に入れ、仮集積所へ集めます。

荒崎海岸は車が入れないので、バケツリレーで、仮集積所から島の中央部へゴミ袋を運びます。

一連の作業の後、昼食、自由時間を過ごし、閉会セレモニー。

再び定期船「とびしま」に乗り、飛島を後にします。
ウミネコが見送ってくれました。

船から見た鳥海山です。

この日の参加者は230名、集めたごみは約2.2トン(主催者発表)とのことです。
天気は快晴でしたが、あまり暑くもなく、さわやかな汗をかきながら飛島をきれいにしたという達成感が得られた1日でした。
来年、是非みなさんも参加してみませんか。 T
Posted by 山形県環境エネルギー部 環境企画課・環境科学研究センター at
17:46
2018年05月28日
里山だより《“オニグルミ”》
【環境科学研究センター】
フジの花が咲き、カッコウの声が響いて、里山は初夏の装いです。

2月に冬芽をご紹介した“オニグルミ”も花を付けました。

下に垂れ下がっているのが雄花です。
大変目立つので「見たことがある!」という方も多いかと思います。
枝の先には赤い雌花も咲いていました。実は、私、初めて見ました。

果実も膨らんできて、成熟するのが楽しみです。

小松沢観音様の参道に、あまり目にすることがないフデリンドウが咲いていました。
ゆっくり季節が過ぎてくれないかと、切に願う今日この頃です。

【おまけ】です。
オニグルミの他にも雄花と雌花を一緒に付ける樹木を見つけました。
ハンノキとツノハシバミです。


フジの花が咲き、カッコウの声が響いて、里山は初夏の装いです。

2月に冬芽をご紹介した“オニグルミ”も花を付けました。

下に垂れ下がっているのが雄花です。
大変目立つので「見たことがある!」という方も多いかと思います。
枝の先には赤い雌花も咲いていました。実は、私、初めて見ました。

果実も膨らんできて、成熟するのが楽しみです。

小松沢観音様の参道に、あまり目にすることがないフデリンドウが咲いていました。
ゆっくり季節が過ぎてくれないかと、切に願う今日この頃です。

【おまけ】です。
オニグルミの他にも雄花と雌花を一緒に付ける樹木を見つけました。
ハンノキとツノハシバミです。


Posted by 山形県環境エネルギー部 環境企画課・環境科学研究センター at
10:17
2018年05月25日
水活~海水浴場の水質検査《採水編》
【環境科学研究センター】
はじめまして。 4月から「水な生活」を送っている T です。
今日から、「水活」と題して、Tの 「水な生活」の一部を、みなさんに不定期でお届けします
第一弾は、海のお話です。
5月も半ばを過ぎ、気温も上昇してきましたね。この先、梅雨が明けたら、いよいよ海水浴シーズンの到来です!!
これに先駆け、県では、庄内総合支庁環境課が中心となって、毎年この時期に、海水浴場の水質検査を行っています。
センターから私が鶴岡方面に、採水のお手伝いに行ってきました。
この日は3班体制で、鶴岡方面の6地点で採水と、2地点で空間放射線測定が目的で、私は船上からの採水を担当しました
まずは、検査に協力いただいく船に道具をのせ、救命胴衣をまとい、いざ出陣!!
この日は快晴ではありませんでしたが、やまがた百名山のひとつ、鳥海山も見えましたよ(※下の写真ではよく見えないですね。肉眼ではしっかり見えたんですよ)。


対象の海水浴場のポイントに到着したら、いよいよ採水。海水を汲んで、容器に移し替えます。
容器は、このあと環境科学研究センターに持ち帰って、検査します(※一部は庄内保健所で検査を行います)。
センターでの検査の模様は、後日このブログで《分析編》でお届けしましょう。
<※由良での様子>


この道具、何かわかりますか?


これは、海の透明度を調べるものです。
白い板の下側に重り(※黄色のもの)があって、全体を海に沈めていって、海面上から白い板が見えている深さを測ります。
紐には目盛りがあって、これで深さがわかります。海水浴場の水質検査では、1メートル以上見えるかどうかを調べます。
今回調べた全ての海水浴場で、1メートル以上見えましたよ。

採水場所では、透明度のほか、油膜の有無、pHを調べました。
みなさんが安心して海水浴場を楽しめるよう、そして夏休みの思い出づくりの一助になればと願い、センターへの帰路についた T でした。
~後日、分析編を掲載予定~
はじめまして。 4月から「水な生活」を送っている T です。
今日から、「水活」と題して、Tの 「水な生活」の一部を、みなさんに不定期でお届けします

第一弾は、海のお話です。
5月も半ばを過ぎ、気温も上昇してきましたね。この先、梅雨が明けたら、いよいよ海水浴シーズンの到来です!!
これに先駆け、県では、庄内総合支庁環境課が中心となって、毎年この時期に、海水浴場の水質検査を行っています。
センターから私が鶴岡方面に、採水のお手伝いに行ってきました。
この日は3班体制で、鶴岡方面の6地点で採水と、2地点で空間放射線測定が目的で、私は船上からの採水を担当しました

まずは、検査に協力いただいく船に道具をのせ、救命胴衣をまとい、いざ出陣!!
この日は快晴ではありませんでしたが、やまがた百名山のひとつ、鳥海山も見えましたよ(※下の写真ではよく見えないですね。肉眼ではしっかり見えたんですよ)。


対象の海水浴場のポイントに到着したら、いよいよ採水。海水を汲んで、容器に移し替えます。
容器は、このあと環境科学研究センターに持ち帰って、検査します(※一部は庄内保健所で検査を行います)。
センターでの検査の模様は、後日このブログで《分析編》でお届けしましょう。
<※由良での様子>


この道具、何かわかりますか?


これは、海の透明度を調べるものです。
白い板の下側に重り(※黄色のもの)があって、全体を海に沈めていって、海面上から白い板が見えている深さを測ります。
紐には目盛りがあって、これで深さがわかります。海水浴場の水質検査では、1メートル以上見えるかどうかを調べます。
今回調べた全ての海水浴場で、1メートル以上見えましたよ。

採水場所では、透明度のほか、油膜の有無、pHを調べました。
みなさんが安心して海水浴場を楽しめるよう、そして夏休みの思い出づくりの一助になればと願い、センターへの帰路についた T でした。
~後日、分析編を掲載予定~
2018年05月14日
里山だより《“立夏”》
【環境科学研究センター】
里山の木々は、次々と芽吹いてきました。
そして、春の花は次から次へなどと言う間もなく、“一気”に咲き誇っています。ご紹介も駆け足になりますが、どうぞお付き合いください。

まずは、【飛ぶ!スプリングエフェメラル】から。
春先にだけ成虫が見られるチョウなども花と同様に「春の女神」と呼ばれることがあります。氷河期の生き残りのヒメギフチョウを見つけました。

ヒメギフチョウはトウゴクサイシンしか食べないそうです。


同じく氷河期の生き残りのウスバシロチョウ(ウスバアゲハ)も間もなく姿を見せてくれることでしょう(昨年の写真です)。

ウスバシロチョウはムラサキケマンしか食べません。北海道の大雪山系に生息するウスバキチョウ(ウスバキアゲハ)はコマクサしか食べないそうです。
次は【咲く!スプリングエフェメラル】です。ムラサキケマン、ヒメニラ(とても小さい)も花を見せてくれました。


では、お約束の木々の花々です。
初めは、以前、“芽”でご紹介したオオバクロモジから、季節が進む順に。

タムシバ、

カスミザクラ、


小松沢観音の参道沿いにあるシダレザクラ(エドヒガン系)、

ヤマモミジ、

ウリハダカエデ、

ヤマツツジ、

ミズナラ、

ウワミズザクラもフワフワと里山を白く彩っています。

春の初めのカタクリの群落は、一面のチゴユリに姿を変えていました。


林の下には、ヒトリシズカが寄り添って咲いています。

ネコノメソウもかわいいですね。

そして、暦の上では“立夏”を過ぎ、シャガまで咲いてしまいました。
中国原産のシャガは、かなり古い時代に日本に入ってきた帰化植物です。種子を付けず、山奥では見られません。薄紫の華やかなシャガの咲く風景は、里山ならではのものです。


里山の木々は、次々と芽吹いてきました。
そして、春の花は次から次へなどと言う間もなく、“一気”に咲き誇っています。ご紹介も駆け足になりますが、どうぞお付き合いください。

まずは、【飛ぶ!スプリングエフェメラル】から。
春先にだけ成虫が見られるチョウなども花と同様に「春の女神」と呼ばれることがあります。氷河期の生き残りのヒメギフチョウを見つけました。

ヒメギフチョウはトウゴクサイシンしか食べないそうです。


同じく氷河期の生き残りのウスバシロチョウ(ウスバアゲハ)も間もなく姿を見せてくれることでしょう(昨年の写真です)。

ウスバシロチョウはムラサキケマンしか食べません。北海道の大雪山系に生息するウスバキチョウ(ウスバキアゲハ)はコマクサしか食べないそうです。
次は【咲く!スプリングエフェメラル】です。ムラサキケマン、ヒメニラ(とても小さい)も花を見せてくれました。


では、お約束の木々の花々です。
初めは、以前、“芽”でご紹介したオオバクロモジから、季節が進む順に。

タムシバ、

カスミザクラ、


小松沢観音の参道沿いにあるシダレザクラ(エドヒガン系)、

ヤマモミジ、

ウリハダカエデ、

ヤマツツジ、

ミズナラ、

ウワミズザクラもフワフワと里山を白く彩っています。

春の初めのカタクリの群落は、一面のチゴユリに姿を変えていました。


林の下には、ヒトリシズカが寄り添って咲いています。

ネコノメソウもかわいいですね。

そして、暦の上では“立夏”を過ぎ、シャガまで咲いてしまいました。
中国原産のシャガは、かなり古い時代に日本に入ってきた帰化植物です。種子を付けず、山奥では見られません。薄紫の華やかなシャガの咲く風景は、里山ならではのものです。


2018年05月10日
県政広報番組「サンデー5」を見てください
【環境科学研究センター】
5月13日(日)17時15分からのYBC「サンデー5」で、当センターの業務が紹介されます。
先日、YBC山川麻衣子アナウンサーから、番組の取材がありました。


冒頭に、一日所長?を命じられた浦安さんが、センター全体の説明をした後、担当者から各業務の紹介をしています。
大気中に漂っている有害物質の常時監視の状況をスマホで確認する方法、
ツキノワグマ生息調査で撮影された、クマの映像なども紹介されます。



詳しくは、番組をご覧ください。
5月13日(日)17時15分からのYBC「サンデー5」で、当センターの業務が紹介されます。
先日、YBC山川麻衣子アナウンサーから、番組の取材がありました。


冒頭に、一日所長?を命じられた浦安さんが、センター全体の説明をした後、担当者から各業務の紹介をしています。
大気中に漂っている有害物質の常時監視の状況をスマホで確認する方法、
ツキノワグマ生息調査で撮影された、クマの映像なども紹介されます。



詳しくは、番組をご覧ください。
2018年05月07日
里山だより《“イノシシとスプリング・エフェメラル”》
【環境科学研究センター】
これまでも何度かイノシシの話題をご紹介しましたが、昔は水田であったと思われる里山の耕作放棄地は、広大なヌタ場(※参照)と化しています。
(※:体についた寄生虫を落とすなどのため、イノシシなどの動物が転げまわった場所)

昨年、この耕作放棄地には、エンレイソウや「スプリングエフェメラル(※参照)」と呼ばれるキクザキイチゲ、ニリンソウなどが群生していたので、今年はどうかと心配していたところでしたが、・・・。
(※:早春に花を咲かせた後には、夏までに葉を枯れさせてしまう一連の野の花の総称)
エンレイソウ、キクザキイチゲが咲き始めました。
遅れて、ニリンソウ、ヤマエンゴサクも見られます。
とりあえず、ほっとしました。





隣地のスギ林に入っていくと、イノシシの気配も消え、可憐なオウレンがひっそりと咲いています。オウレンの根茎を乾燥したものは、漢方薬として用いられています。

小松沢観音様に登っていくと、同じく「スプリングエフェメラル」のショウジョウバカマ、カタクリが咲いていました。
「スプリングエフェメラル」の多くは、天候が悪くて日差しが弱いと、花を閉じてしまいます。春の柔らかな光の中に咲く【春の妖精】達に心癒されます。


スミレやキバナイカリソウも咲き始め、春は早足に通り過ぎて行くんですね。


木々も次々と芽吹き、その花も咲き始めていますが・・・、次回でご容赦ください。
これまでも何度かイノシシの話題をご紹介しましたが、昔は水田であったと思われる里山の耕作放棄地は、広大なヌタ場(※参照)と化しています。
(※:体についた寄生虫を落とすなどのため、イノシシなどの動物が転げまわった場所)

昨年、この耕作放棄地には、エンレイソウや「スプリングエフェメラル(※参照)」と呼ばれるキクザキイチゲ、ニリンソウなどが群生していたので、今年はどうかと心配していたところでしたが、・・・。
(※:早春に花を咲かせた後には、夏までに葉を枯れさせてしまう一連の野の花の総称)
エンレイソウ、キクザキイチゲが咲き始めました。
遅れて、ニリンソウ、ヤマエンゴサクも見られます。
とりあえず、ほっとしました。





隣地のスギ林に入っていくと、イノシシの気配も消え、可憐なオウレンがひっそりと咲いています。オウレンの根茎を乾燥したものは、漢方薬として用いられています。

小松沢観音様に登っていくと、同じく「スプリングエフェメラル」のショウジョウバカマ、カタクリが咲いていました。
「スプリングエフェメラル」の多くは、天候が悪くて日差しが弱いと、花を閉じてしまいます。春の柔らかな光の中に咲く【春の妖精】達に心癒されます。


スミレやキバナイカリソウも咲き始め、春は早足に通り過ぎて行くんですね。


木々も次々と芽吹き、その花も咲き始めていますが・・・、次回でご容赦ください。