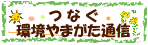2023年01月30日
手づくり門松(動画あり)
令和5年も1月中旬を過ぎ松も取れましたが、昨年末に兎年の年神様を迎えるために手づくりで門松作りを行いました。
門松には、年中落葉しない「松」とめでたい赤い実の「南天」(難を転ずるの意もあり)、成長の早い「竹」を使います。
このうち、成長の早い「竹」については、間伐をしないと里山の他の植物が育たなくなってしまいます。この間伐した「竹」が、おめでたい門松作りにも役立ち、一挙両得です。
動画の前半は、作り方を説明していますので、DIY派の方に限らず是非参考になさってください。
●手づくり門松

●講師による説明

●作る人の個性が出ます




☆☆動画は以下からご覧ください。☆☆
https://youtu.be/JpwO7A0PjY8

動画は上記画像からもアクセスできます。
【問合せ先】
山形県環境科学研究センター
村山市楯岡笛田3-2-1
TEL0237-52-3121、FAX0237-52-3135
メール:ykankyose@pref.yamagata.jp
門松には、年中落葉しない「松」とめでたい赤い実の「南天」(難を転ずるの意もあり)、成長の早い「竹」を使います。
このうち、成長の早い「竹」については、間伐をしないと里山の他の植物が育たなくなってしまいます。この間伐した「竹」が、おめでたい門松作りにも役立ち、一挙両得です。
動画の前半は、作り方を説明していますので、DIY派の方に限らず是非参考になさってください。
●手づくり門松

●講師による説明

●作る人の個性が出ます




☆☆動画は以下からご覧ください。☆☆
https://youtu.be/JpwO7A0PjY8

動画は上記画像からもアクセスできます。
【問合せ先】
山形県環境科学研究センター
村山市楯岡笛田3-2-1
TEL0237-52-3121、FAX0237-52-3135
メール:ykankyose@pref.yamagata.jp
Posted by 山形県環境エネルギー部 環境企画課・環境科学研究センター at
17:13
2023年01月23日
「気候変動適応」研修会(動画あり)
国連の気候変動に関する会議の中で、気温上昇の1.5℃目標が定められ、そのために世界のCO2排出量を今世紀半ばまでに実質ゼロにすることが必要となっています。
そうした中で、農業や自然災害等の温暖化の影響が避けられない分野については、うまく対処してくことが求められており、「気候変動適応」策として対策を講じていくことが重要となります。
「気候変動適応法」では、「地域気候変動適応計画」を策定することが、各自治体(市町村等)の努力義務とされており、研修会では、計画の必要性や実際の策定経過、気象データの推移などについて国立環境研究所や鶴岡市、山形地方気象台からお話いただきました。
約3分の動画にまとめましたので、「気候変動適応」の基本の理解にお役立てください。
●気候変動適応研修会

●国立環境研究所 町村研究調整主幹
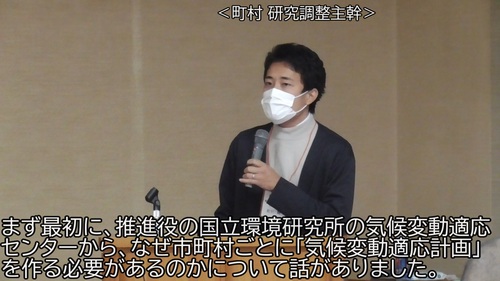
●国立環境研究所 伊藤高度技能専門員

●山形地方気象台 藤原調査官

●鶴岡市 北山氏

●ワークショップ

☆☆動画は以下からご覧ください。☆☆
https://youtu.be/v-aXN_7_Fcs

動画は上記画像からもアクセスできます。
【問合せ先】
山形県環境科学研究センター
村山市楯岡笛田3-2-1
TEL0237-52-3121、FAX0237-52-3135
メール:ykankyose@pref.yamagata.jp
そうした中で、農業や自然災害等の温暖化の影響が避けられない分野については、うまく対処してくことが求められており、「気候変動適応」策として対策を講じていくことが重要となります。
「気候変動適応法」では、「地域気候変動適応計画」を策定することが、各自治体(市町村等)の努力義務とされており、研修会では、計画の必要性や実際の策定経過、気象データの推移などについて国立環境研究所や鶴岡市、山形地方気象台からお話いただきました。
約3分の動画にまとめましたので、「気候変動適応」の基本の理解にお役立てください。
●気候変動適応研修会

●国立環境研究所 町村研究調整主幹
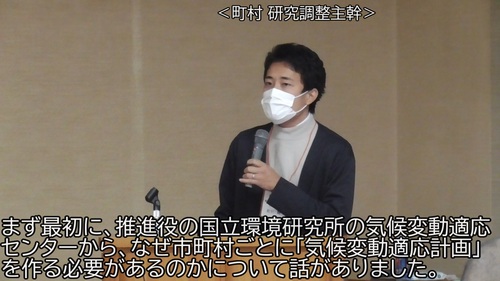
●国立環境研究所 伊藤高度技能専門員

●山形地方気象台 藤原調査官

●鶴岡市 北山氏

●ワークショップ

☆☆動画は以下からご覧ください。☆☆
https://youtu.be/v-aXN_7_Fcs

動画は上記画像からもアクセスできます。
【問合せ先】
山形県環境科学研究センター
村山市楯岡笛田3-2-1
TEL0237-52-3121、FAX0237-52-3135
メール:ykankyose@pref.yamagata.jp
Posted by 山形県環境エネルギー部 環境企画課・環境科学研究センター at
15:56
2023年01月17日
冬の野山“フィールドサイン編”
冬の晴れ間に月山の麓を歩いてみました。ブナ林を見ると、ノウサギの足跡が続いています。カラマツの木の下では、だれかが食べた実を発見!犯人はニホンリスでした。冬の野山は動物達の#フィールドサインが一杯!動物を身近に感じることができますよ。
#つなぐ環境やまがた





#つなぐ環境やまがた
Posted by 山形県環境エネルギー部 環境企画課・環境科学研究センター at
15:56
2023年01月17日
R5研究計画発表会(動画あり)
山形県環境科学研究センターでは、毎年9月から10月にかけて次年度の研究計画の発表会を実施しています。
SDGsが皆さんに認識され、環境への関心がこれまで以上に高まってきている中で、環境に関する課題は多様化してきています。
そうした課題を解決するため、若手を中心に新たな研究に取り組んでいます。
今回は、今年度からの継続案件も含めたR5年度に向けた研究計画の発表と山形大学理学部の亀田教授によるアドバイザリーボードの様子ついてご紹介します。
●VOCの実態調査 【荒木研究員】

●アナモックス菌を用いた脱臭システムの構築 【西塚主任専門研究員】

●最上川でのマイクロプラスチック調査 【笠原専門研究員】

●ダイオキシン類の流出実態調査 【新藤主任専門研究員】

●災害時等の化学物質流出の迅速な測定法 【森田専門研究員】

●アドバイザリーボード 【山形大学理学部 亀田教授】
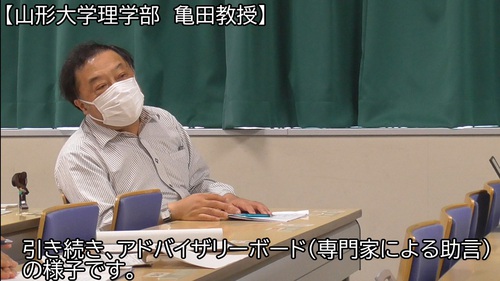
☆☆動画は以下からご覧ください。☆☆
https://youtu.be/dBpg7Fn9RMk
動画は上記画像からもアクセスできます。

【問合せ先】
山形県環境科学研究センター
村山市楯岡笛田3-2-1
TEL0237-52-3121、FAX0237-52-3135
メール:ykankyose@pref.yamagata.jp
SDGsが皆さんに認識され、環境への関心がこれまで以上に高まってきている中で、環境に関する課題は多様化してきています。
そうした課題を解決するため、若手を中心に新たな研究に取り組んでいます。
今回は、今年度からの継続案件も含めたR5年度に向けた研究計画の発表と山形大学理学部の亀田教授によるアドバイザリーボードの様子ついてご紹介します。
●VOCの実態調査 【荒木研究員】

●アナモックス菌を用いた脱臭システムの構築 【西塚主任専門研究員】

●最上川でのマイクロプラスチック調査 【笠原専門研究員】

●ダイオキシン類の流出実態調査 【新藤主任専門研究員】

●災害時等の化学物質流出の迅速な測定法 【森田専門研究員】

●アドバイザリーボード 【山形大学理学部 亀田教授】
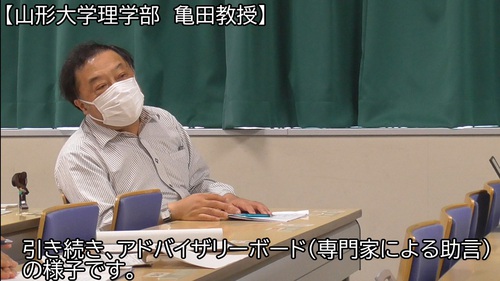
☆☆動画は以下からご覧ください。☆☆
https://youtu.be/dBpg7Fn9RMk
動画は上記画像からもアクセスできます。

【問合せ先】
山形県環境科学研究センター
村山市楯岡笛田3-2-1
TEL0237-52-3121、FAX0237-52-3135
メール:ykankyose@pref.yamagata.jp
Posted by 山形県環境エネルギー部 環境企画課・環境科学研究センター at
14:14