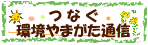2018年05月14日
里山だより《“立夏”》
【環境科学研究センター】
里山の木々は、次々と芽吹いてきました。
そして、春の花は次から次へなどと言う間もなく、“一気”に咲き誇っています。ご紹介も駆け足になりますが、どうぞお付き合いください。

まずは、【飛ぶ!スプリングエフェメラル】から。
春先にだけ成虫が見られるチョウなども花と同様に「春の女神」と呼ばれることがあります。氷河期の生き残りのヒメギフチョウを見つけました。

ヒメギフチョウはトウゴクサイシンしか食べないそうです。


同じく氷河期の生き残りのウスバシロチョウ(ウスバアゲハ)も間もなく姿を見せてくれることでしょう(昨年の写真です)。

ウスバシロチョウはムラサキケマンしか食べません。北海道の大雪山系に生息するウスバキチョウ(ウスバキアゲハ)はコマクサしか食べないそうです。
次は【咲く!スプリングエフェメラル】です。ムラサキケマン、ヒメニラ(とても小さい)も花を見せてくれました。


では、お約束の木々の花々です。
初めは、以前、“芽”でご紹介したオオバクロモジから、季節が進む順に。

タムシバ、

カスミザクラ、


小松沢観音の参道沿いにあるシダレザクラ(エドヒガン系)、

ヤマモミジ、

ウリハダカエデ、

ヤマツツジ、

ミズナラ、

ウワミズザクラもフワフワと里山を白く彩っています。

春の初めのカタクリの群落は、一面のチゴユリに姿を変えていました。


林の下には、ヒトリシズカが寄り添って咲いています。

ネコノメソウもかわいいですね。

そして、暦の上では“立夏”を過ぎ、シャガまで咲いてしまいました。
中国原産のシャガは、かなり古い時代に日本に入ってきた帰化植物です。種子を付けず、山奥では見られません。薄紫の華やかなシャガの咲く風景は、里山ならではのものです。


里山の木々は、次々と芽吹いてきました。
そして、春の花は次から次へなどと言う間もなく、“一気”に咲き誇っています。ご紹介も駆け足になりますが、どうぞお付き合いください。

まずは、【飛ぶ!スプリングエフェメラル】から。
春先にだけ成虫が見られるチョウなども花と同様に「春の女神」と呼ばれることがあります。氷河期の生き残りのヒメギフチョウを見つけました。

ヒメギフチョウはトウゴクサイシンしか食べないそうです。


同じく氷河期の生き残りのウスバシロチョウ(ウスバアゲハ)も間もなく姿を見せてくれることでしょう(昨年の写真です)。

ウスバシロチョウはムラサキケマンしか食べません。北海道の大雪山系に生息するウスバキチョウ(ウスバキアゲハ)はコマクサしか食べないそうです。
次は【咲く!スプリングエフェメラル】です。ムラサキケマン、ヒメニラ(とても小さい)も花を見せてくれました。


では、お約束の木々の花々です。
初めは、以前、“芽”でご紹介したオオバクロモジから、季節が進む順に。

タムシバ、

カスミザクラ、


小松沢観音の参道沿いにあるシダレザクラ(エドヒガン系)、

ヤマモミジ、

ウリハダカエデ、

ヤマツツジ、

ミズナラ、

ウワミズザクラもフワフワと里山を白く彩っています。

春の初めのカタクリの群落は、一面のチゴユリに姿を変えていました。


林の下には、ヒトリシズカが寄り添って咲いています。

ネコノメソウもかわいいですね。

そして、暦の上では“立夏”を過ぎ、シャガまで咲いてしまいました。
中国原産のシャガは、かなり古い時代に日本に入ってきた帰化植物です。種子を付けず、山奥では見られません。薄紫の華やかなシャガの咲く風景は、里山ならではのものです。